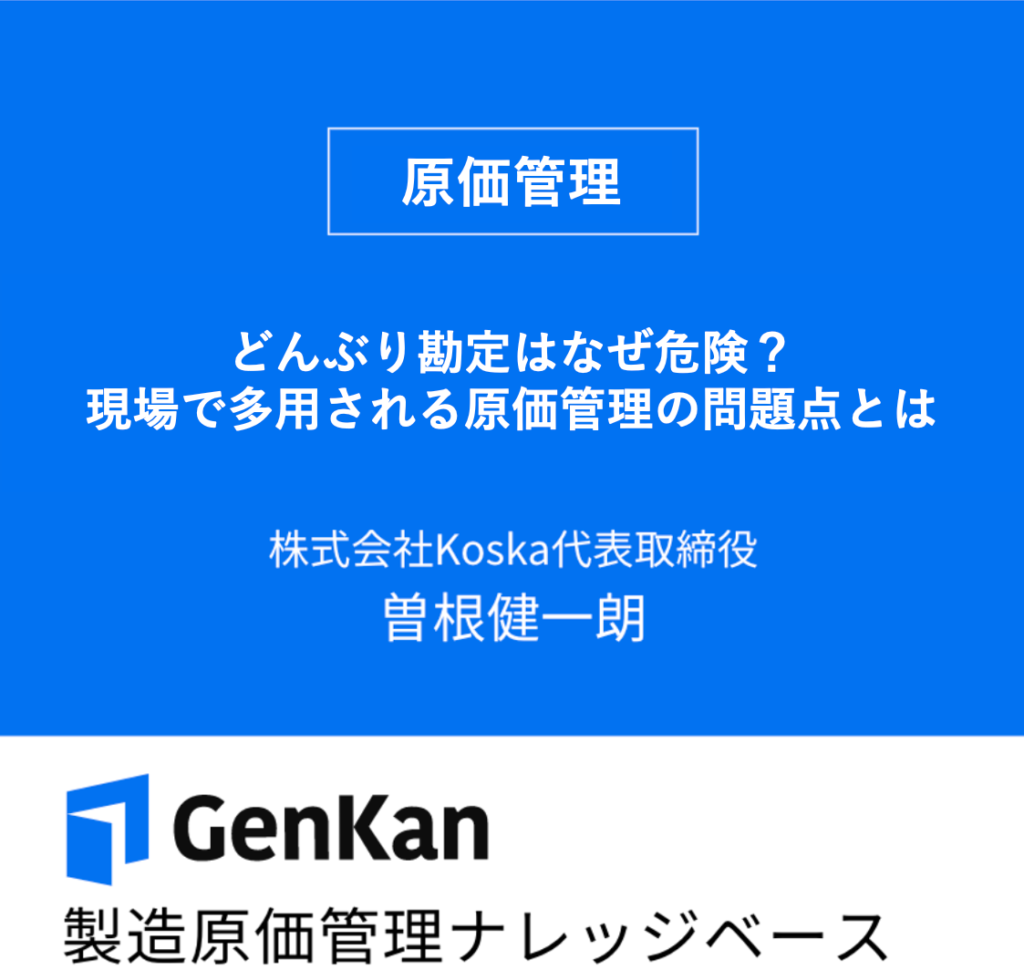
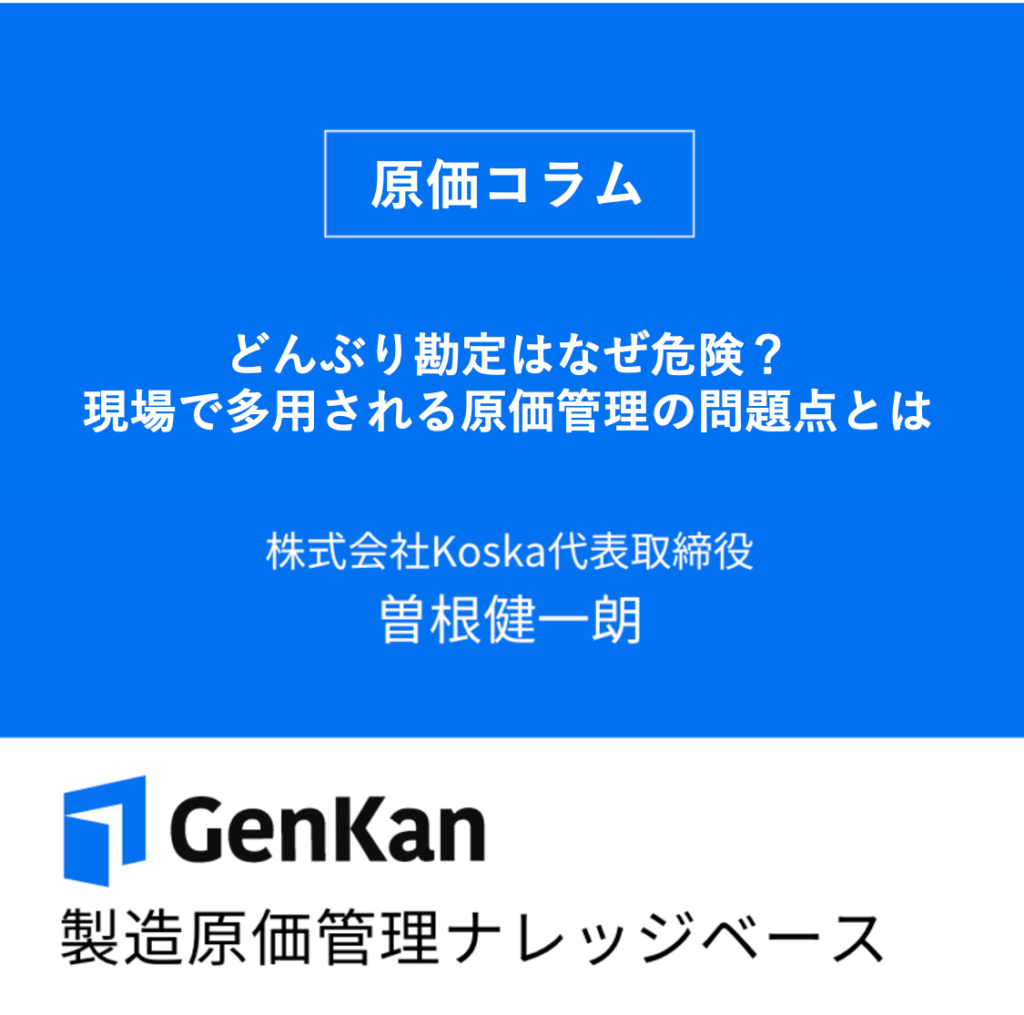
前回のブログではサイクルタイムの分析についてお伝えしましたが、本ブログは原価管理において中小企業で主に用いられている方法を2つピックアップし、それが経営に与えるデメリットや改善の方向性を簡単に説明します。
1. どんぶり勘定
収支の管理を会社全体で行い、製品ごとの収支を把握しないことをどんぶり勘定と呼びます。この場合、下記のように現場の担当者からは多くの相談を受けることがあります。
・会社全体が赤字だけど、それの原因がどこにあるか分からない
・毎月十数万点生産している主力製品があるが、それにかかった費用が分からない
・赤字の製品があるかもしれないが、調べようがない。
どんぶり勘定による会計は百害あって一利なしと言われるほどデメリットが多いです。唯一のメリットに、会計における知識や計算の必要がなく、短期的に見れば会計担当の方の手間や時間が省けることが挙げられます。一方で、気付かないうちに赤字の製品を作り続けた結果、期間損益の収支が悪化となってしまうことや、それと同時に、このような収支悪化の原因が分からず、財務情報が経営判断の根拠に使えなくなるなどの深刻なデメリットがあります。
こうしたデメリットを払拭しどんぶり勘定から脱却するには、製品ごとに収支を管理して行く必要があります。しかし、全てをいきなり管理するのは厳しい場合もあるので、まずは主力製品から進めていくのも一つの得策です。
2. 数年に一度行われる原価管理
どんぶり勘定に次いで多いのが、最新の現場状況を原価管理に反映できていないというケースです。多くの製造現場では、大口受注の際、見積書を改めるためにストップウォッチを用いた生産速度の計測を行い、労務費や機械経費を考慮の上で製品の見積原価を算出しています。
一見すると原価管理が出来ているように見えますが、製品の実際原価は製造の中断や作業者の熟練度などの理由から常に変動しています。一度決めた見積原価を長い間変更せずに使い続けてしまうと、様々な問題が生じてきます。
例えば、もともと黒字で想定していた製品に関し、数年経った後、現場の変化により実際原価が見積原価より上回った場合、気づかないうちに実は赤字注文を繰り返していたという事態が発生する可能性があります。一方で、本来赤字であるべき製品に対し、作業員の努力により実際原価が見積原価より下回った場合、作業員が正当に評価されておらず、さらなる原価改善を妨げることになるかもしれません。
このような事態を防ぐためには、なるべく短い期間で見積書を見直すとともに、原価を算出し直すと良いでしょう。毎月の原価改修が難しい場合、四半期または年一度でも良いので原価を見直しすることをおすすめします。
以上、製造現場においてよく用いられている原価管理の方法をお伝えしました。
このように、理想とは程遠い原価管理を行う企業も数多く存在しますが、中には意識的に原価管理を取り入れて赤字製品をゼロにした企業も存在します。製造業(特に中小企業)の実態と彼らが取り組んできた内容について、今後もブログを公開していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!

