Genkanを開発しているKoskaオフィスには至る所に岡本清先生の『原価計算』が置かれています。
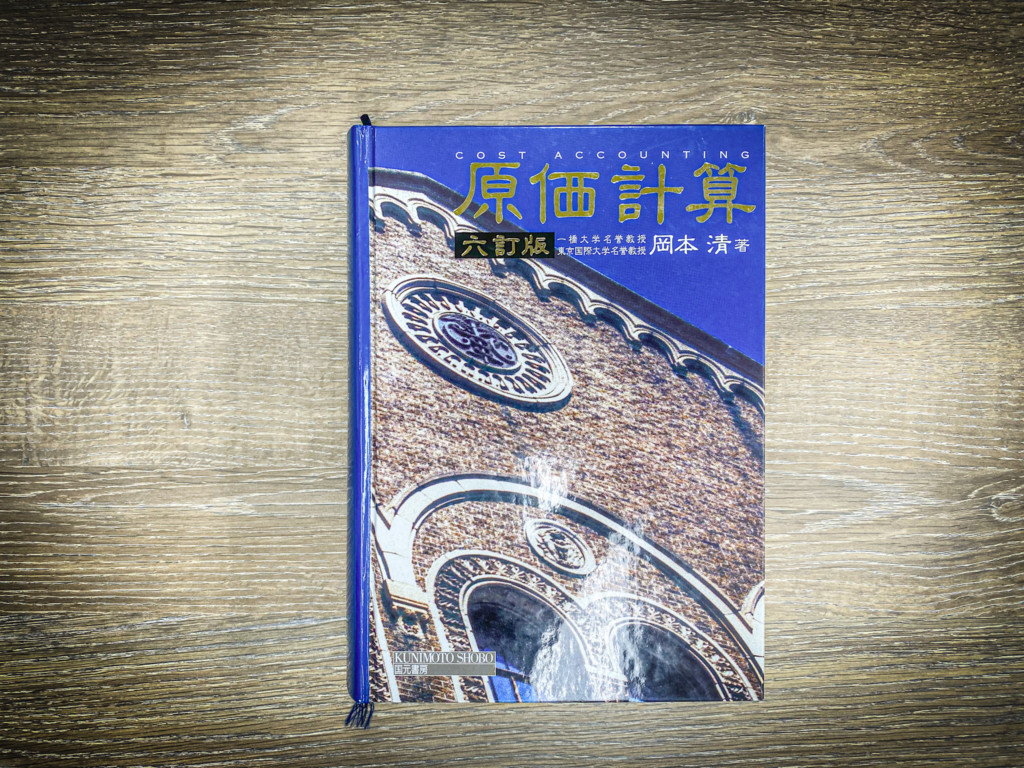
開発や分析、様々な場面で社内では原典/聖書と呼ばれているこの青い本をひきます。
今回は第4章3節まで、それぞれについて要点をまとめてみました。
この部分をもっと詳しく解説して欲しい、この部分がわからないといった点、コメントいただければ原価の専門家がご要望に応じて追加で記事を執筆いたします。
是非お気軽にコメントください!
第1章 原価計算の基礎知識
第1節 原価計算の意義
- 企業の経済的データ処理システムとしての原価計算と、情報処理システムとしての原価計算がある。
- 前者では、原価計算は、企業の会計情報システムとして、複式簿記と対をなすものとして捉えられる。
- 重要なのは、原価計算は原価(インプット)のみに注力しても意味がなく、給付(アウトプット)と原価(インプット)を比較して初めて有用なものとなるということである。
- ここで給付とは、最終巻製品のみでなく、部門給付をも意味する。
- 製品原価計算は、原価計算の扱う領域の一部分にすぎず、原価計算の目的は複数存在し、「構造意思決定目的」「業務意思決定目的」「利益管理目的」「原価管理目的」「公開財務諸表作成目的」などに分類することができる。
- 原価計算の目的が原価管理目的であるとするとき、原価は発生の場所で、責任者別に集計しなければならない。
- 原価計算の目的が原価管理目的のとき、会計期間は短いほど良く、毎日、毎週、毎月の原価を計算し報告する必要がある。
- 原価計算の目的が原価管理目的のとき、管理者にとって管理可能費か、管理不能費かが問題となる。
- 著者による原価計算の定義「原価計算とは、企業を巡る利害関係者、とりわけ経営管理者に対して企業活動から発生する原価、利益などの財務的データを、企業給付に関わらしめて、認識し、測定し、分類し、要約し、解説する理論と技術である。」
第2節 原価の一般概念
- 原価計算は、常時継続的に行われる原価計算制度と、必要な時に随時行われる特殊原価調査とからなっている。
- 原価は、有形、無形の「経済的価値のある財貨」を「消費」したときに発生する。ゆえに、消費しても経済的価値のないものであれば原価にならない。また、経済的価値のある財貨であっても消費しなければ原価とはならない。
- 財貨が消費されると、経済的価値は、消費の結果生じた給付に乗り移ると考えられる。
- 企業における本業以外を目的として消費された時に生じたコストは原則原価と認めない。(資本調達の際発生したコストなど)
- 異常事態のもとコストが発生した時、それは原価とは認めない。
- 原価計算制度は国によって全く異なる
- 原価は支出原価と機会原価の2つに分類して捉えることができる。
- 支出原価とは支払われた現金支出額によって測定した原価である。
- 機会原価とは、実際に支出があった用途以外にその支出を振り向けたならば得られたはずの最大利益額によって測定する原価である。
- 機会原価は経営判断に用いられることがあるが、これを測定するのは非常に難しい。
第3節 原価の基礎的分類
- 形態別分類と製品との関連における分類ができる。
- 形態別分類を行った時、原価は材料費、労務費、経費に分けることができる。
- 製品との関連における分類をした時、原価は直接費と間接費に分けることができる。
第4節 コスト・フローと原価計算の手続
- 原価計算では、原価の流れを追跡する。
- 製品が販売される、またはサービスが消費される前のコストは資産であり、原価とはみなされない。販売、消費されて初めて原価となるのである。
- 原価の流れを追跡する場合、その計算は費目別計算、部門別計算、製品別計算の順で行われる。
- 費目別計算は、消費した財貨の種類によって原価要素を認識し、計算する手続きである(計算じゃないの?)
- 部門別計算は、原価要素を、原価の発生した場所別に分類し、計算する手続きである。
- 部門別計算は、原価の責任者別に原価を集計することができるため、責任の所在を明らかにすることができるという意味で重要である。
- 部門別計算で注意すべき点は、単に発生場所のみによる分類を行うのではなく、費目別、部門別に計算することである。
- 製品別計算は、原価要素を製品別に分類し、計算する手続きである。内部や外部への報告目的で重要な計算方法である。
第5節 原価単位と原価計算期間
- 原価単位とは、原価に関係付けられる給付の単位である。
- 原価単位は、売価を決定するため、また各部門の業績を評価するために用いられる。
- 原価計算期間は原価報告を行うための一定の期間のことである。
- 原価計算期間は1ヶ月とするのが通常であるが、経営管理のためには、短ければ短いほど良い。
第6節 原価計算の種類と形態
全部原価計算と直接原価計算
- 原価計算は伝統的接近方法を採用するか、貢献利益的接近方法を採用するかで全部原価計算と直接原価計算に分類できる。
- 全部原価計算は売価決定を目的として誕生したという歴史があり、職能別原価分類が重視される。
-全部原価計算において、全ての原価は、収益に対して同程度貢献したと考えられる。(原価の同質性) - 原価の同質性より、伝統的な損益計算では、全ての原価は製品原価として製品に集計できるとしているが、現実にはこれは不可能であるため、製品に直接結びつけることのできない原価は期間原価として別に処理される。
- 理想は全ての原価を製品原価に集約することであり、期間原価は必要悪である。
- 直接原価計算は、経営活動量と原価の関係を考察する目的で誕生したという背景から、変動費、固定費の分類が重視される。
- 直接原価計算では、原価は収益との関連に置いて異質的である。ここに貢献利益の考えが生じる。
実際原価計算、見積もり原価計算、標準原価計算
- 原価は、製造を行う前に予定するか、製造を行った後に算定するかで、予定原価と実際原価に分類され、予定原価はさらに見積もり原価と標準原価に分けることができる。
- 大抵の場合、見積もり原価は間違っていることを前提とし、標準原価は正しいことが前提とされるが、この2つを厳密に区別する明確な基準はない。
個別原価計算と総合原価計算
- 製品の生産形態の違いで採用する原価計算が個別原価計算と総合原価計算に分かれる。
- 個別原価計算は一品一様の生産や、少量多品種生産向けの原価計算である。
- それぞれの製品が他の製品と区別され、加工されるとき個別原価計算が用いられる。
- 個別原価計算をとるべき代表的な経営の例は、受注生産経営である。
- 個別原価計算には製造間接費について部門別計算を行う部門別個別原価計算(中小企業向け)と、製造間接費について部門別計算を行わない直接個別原価計算(大企業向け)とがある。
- 総合原価計算は量産の生産形態向けの原価計算である。
- 総合原価計算は、1原価計算期間に生産された1製品あたりの平均原価を知ることに主眼がある。
- 総合原価計算には、単純総合原価計算と等級別総合原価計算、組別総合原価計算がある。
- 単純総合原価計算は、1種類のみの製品の生産向けで、等級別総合原価計算は、大きさや形状で区別された製品の生産向け、組別総合原価計算は異種製品を組別に連続生産する生産形態向けである。
第7章 原価計算と責任会計
- 原価計算は経営管理者に利益管理のための重要な情報を提供するが、これが企業の組織と結びついて、改善に活かされなければ意味がない。そこで誕生したのが責任会計の考え方である。
- 企業が持つ責任センターの範囲の定めかたは企業によって様々であるが、会計の見地からすれば、原価(責任)センター、利益(責任)センター、投資(責任)センターの3つに分類することができる。
- 原価センターは原価にのみ責任をもち、利益センターは原価センターの責任に加えて収益に対しても責任を負い、投資センターは利益センターの責任に加えて投資活動の権限を持つ。
- 責任会計とは、「企業組織内における責任センターを識別し、各センターの業績を明らかにするために、各センターにたいし、それぞれが責任をもつ特定の原価、収益、投資額を割り当て、各センター別に、計画と実績、および差異にかんする財務情報を提供する会計システム」(『原価計算』岡本清、国元書房)である。
- 原価業績報告書では、管理可能費についての予算、実績、及び差異を示す。
- 第一線の現場管理者には、管理可能費のみに限定した報告書、より上級レベルの管理者には管理可能項目と管理不能項目とを区別した報告書が提出される。
- 企業は勘定科目分類表作成するが、この基本的な狙いは財務会計目的と管理会計目的の両方に役立つような情報システムを作ることにある。
- 管理可能費と管理不能費の区別は特定の責任センターの管理者によって管理可能か否かで決まるが、この可否が業績測定期間の長短によって異なること、1責任センターが全てを管理することは不可能であることなどを鑑みると、この区別は単純明快なものではなく、しばしばトラブルの原因になる。
- 2つ以上の責任センターにまたがって発生する原価を共通費と呼ぶが、この配布額はその責任センターの長にとって一般には管理不能であるから、責任会計上は、できる限り原価を個別費と捉えるのが望ましい。
- 経営活動の量に応じて、変化する原価の様子を、コスト・ビヘイビァーという。
- 経営活動の量に応じて原価を変動費、固定費、準変動費、準固定費の4つに分類することができ、それぞれでコスト・ビヘイビァーは類型できる。
第2章 商的工業会計ー原価計算以前の工業会計ー
- 商的工業会計は丼勘定方式とも呼ばれ、原価計算を採用していない中小の企業では大抵これが用いられている。
第1節 商的工業会計の計算原理
- 商業簿記で売上原価や売上利益を計算するもっとも簡単な方法は、混合勘定として商品勘定を利用する方法であるが、この「商品」を「製造」にして勘定を出したものが丼勘定の原型である。
- 計算方法は棚卸計算方法に基づいている。
第2節 商的工業会計の欠陥と原価計算の誕生
- 商的工業会計の長所は、計算事務に手間がかからず、そのため事務費用が少なくてすむという点にある。
- 企業の規模が小さい場合には経営者が工場を歩き回ることで状況を把握し、必要な時に命令を下すことができることから、商的工業会計でも十分である。
- 丼勘定方式では、製品別の実際原価が不明であるから、売価決定に役立つ原価資料がえられないという短所がある。
-丼勘定方式には会計期間の途中では、企業が儲かっているのかさえわからないという短所がある。 - 丼勘定方式では、製品別の実際原価が不明なので、どの製品が儲かっているのかが分からないという短所がある。
第3章 見積原価計算
- 見積原価計算は、原価計算のもっとも古い形態の1つであるが、現在でもよく使われる。
第1節 見積原価計算の計算原理
- 原価見積は、原価単位あたりの実際製造原価を、非科学的方法により予定した額である。
- 見積原価は、原価見積にその製品の実際生産量を乗じた額をさす。
- 実際生産量は実際に生産したあとでなければ計算できない。
- 丼勘定方式の計算を実施する場合には、原価見積が不可欠の計算要素である。つまり、勘で出した原価を使わざるをえないのである。
- 丼勘定方式を採用する企業において原価見積もりが不正確のとき、売価を正確に決めることができないため、儲かっていると思い込んでいながら実は損をしているということが起こりうる。
- また仕掛品と製品の期末有高が不正確になり期間損益計算もまた不正確になる。
- 原価見積もりの正確性をチェックする方法として、製品の実際製造原価と原価見積もりとを直接比較する方法がある。
- 製品の実際製造原価を出すためには、リアルタイムの原価の移り変わりを追跡し、集計し、計算する必要がある。
- 原価見積と見積原価が実績と異なる値を出した時は見積もりが誤っていたと考える。
- 見積原価と実績が一致したとしても、異なる2つの勘定科目がそれぞれ誤っていて、相殺した結果、数字が一致しているということもある。(直接材料費の見積もりが実際より高く、直接労務費の見積もりが実際より低いなど。)
第2節 見積原価計算の長所と短所
- 見積原価計算の長所は簡略化することで、事務経費を節約することができることにある。
- 見積原価計算の短所は簡略化によって、正確さが失われること、詳細さに欠けてしまうことにある。
- 例えば見積計算では、原価見積が間違っていることが分かっても、どの部門の原価見積が誤まっていたのかまたどの部品の原価見積が誤まっていたのかなどの詳細を知ることができない。
- 見積原価計算において計上される実際直接材料費は、棚卸計算方法によって算出された材料費で、これは実際の直接材料費を示さない。
- なぜなら材料の蒸発や損失などといった材料の量の変化が考慮に入れられていないからである。
- 上記の問題を解決するために採用されたのが「継続記録法」であるが、これには膨大なコストが生じる。
- 棚卸計算方法では、製品に材料費を紐づけることが難しい。
- 上記の理由から、材料費を直接材料費と間接材料費とに区別して計算することができない。
第4章 実際原価計算総説および実際単純個別原価計算
第1節 実際原価計算総説
- 実際原価は偶発的な要素に左右されるため、昔は真実の原価(true costs)であると考えられていたが、現在では偶発的な原価(accidental costs)であるとするのが一般的である。
-実際原価の概念は、歴史的原価(historical costs)から実際正常原価(actual normal costs)へと変化してきた。 - 歴史的原価では、原価は原価材の価格に実際に生じた消費量を掛けて計算される。
- 歴史的原価を求める際、価格要素も消費量要素も、全くそのときどきの実際によって計算されるため、原価は異常事態に左右される。
- 原価が異常事態によって左右されると、原価管理目的や、損益勘定目的に利用し辛いと言う理由で誕生したのが実際正常原価計算であり、現在実際原価計算というと実際正常原価計算を示す。
- 実際正常原価計算では、異常な財貨消費額は、非原価項目として除去し、あるいは数期間に平均化する。
- 「製品原価とは、一定単位の製品に集計された原価をいい、期間原価とは、一定期間における発生額を、当期の収益に直接対応させて、把握した原価をいう。」(「基準」第1章4(2))。
- 可能であれば、全てのコストを全て製品原価として計算することが望ましいのであるが、実際にはそれは不可能である。
- なぜなら販売費および一般管理費のほとんどは、製品に合理的に集計することは困難だからである。
- そこで誕生したのが期間原価であり、製品に紐付けることが困難な原価を、期間原価として、発生した期間の収益から直接に回収するという方法をとる。
- 期間原価はあくまで必要悪という立場にあり、可能であれば全て製品原価として集計するのが望ましい。
第2節 実際単純個別原価計算とその方法
- 正式な原価計算は、 1費目別計算、2部門別計算、3製品別計算という手順を踏んで行われる。
- 抽象企業の原価計算は、1費目別計算、2製品別計算という手順を踏むことが多く、このような個別原価計算のことを、単純個別原価計算という。
-個別原価計算は、出庫票から直接材料費を、作業時間報告書から直接労務費を、外注加工品受払帳などから直接経費を割り出し(上記3つの費用を合わせて製造直接費とする)、製造間接費配賦票から製造間接費を計算する。 - 製造直接費は、各々の製造指図書番号の原価計算票へ移記する。これを、製造直接費の直課という。
- 製造間接費は、各指図書別に計算することができないため、直接作業時間を基準にして製造間接費の実際配賦率を計算する。
- 製造間接費の実際配賦率=1ヶ月間の製造間接費実際発生額/同期間の実際直接作業時間
- 製造間接費の実際配賦は、原因が特定できないため望ましくないとされる。製造間接費は実際額を配賦するのではなく、年間を通じ一定の正常額を配賦するのが普通である。
- 製造間接費の正常配賦率=1年間の製造間接費予算/同期間の予定総直接作業時間数
- 特定の製品にたいする製造間接費の正常配賦額=製造間接費の正常配賦率×その製品の製造に要した実際直接作業時間数
第3節 材料費会計
-材料は常備材料と引当材料に分類できる。(実務で使われる機会は少ない)
- 材料費は材料を消費した時発生すると考えられるが、実務では出庫票によって材料が出庫される時、その出庫を持って消費とみなすこともある。
- 材料費は、その製品の主たる実態を構成するときに消費される材料である直接材料費と、それ以外の間接材料費とに分類することができる。
- 間接材料費には2種類あり、材料が製品構造のために消費され、その製品の実態を構成するけれども、金額的に重要ではないかその消費額を計算することが不経済な材料の原価と、製品の実態を構成しない材料の原価とがある。
- 実務では、間接材料費を金額的に重要か否かで2つに分類している。
- 金額的に重要な間接材料の消費額を補助材料費として出庫票を使用し受払記録をつけて管理している。
- 金額的に重要でない間接材料の消費額を工場消耗品費としている。
-材料購入原価は、理論上と実務上で勝手が異なる。 - 理論上は、材料購入原価=材料購入代価+材料引取費用+材料取扱・保管費によって計算すべきとされる。
- 実務上は、材料購入原価=材料購入代価+材料引取費用とし、材料取扱・保管費は、間接経費として、他の製造間接費と共に、直接作業時間などを基準にして、製品へ配賦する方法をとることが多い。
- 受払記録を行う材料については、材料費=その材料の実際消費単価×その材料の実際消費量によって計算する。
- 材料実際消費量を把握するために、継続記録法(コストはかかるが正確)と、棚卸計算法が存在する。
- 材料実際消費単価は、その材料の購入単位原価であるが、同じ材料を異なる単価で仕入れた場合は、様々な算出法がある。
- 先入先出法、移動平均法、月次総平均法、継続的後入先出法、期間的後入先出法が存在する。
- 実際材料消費単価を計算する方法としては個別法がもっとも正確な方法であると考えられていたが、実施困難であるばかりか、購入単価がいちじるしく変動する際に材料単価の偶然的な変動が、製品原価にそのまま影響するという欠点がある。
- 先入先出法では、金の流れと物の流れが一致するので、企業活動の現実に即した方法であると捉え、適用する会社が多い。
- 移動平均法と総平均法は、材料の購入単価における偶発的な変動を平均化することができるというメリットがある。(これもよく適用される)
– 後入先出法は、物価の上昇に基づく突発利益を期間利益から除去することができるというメリットがある

